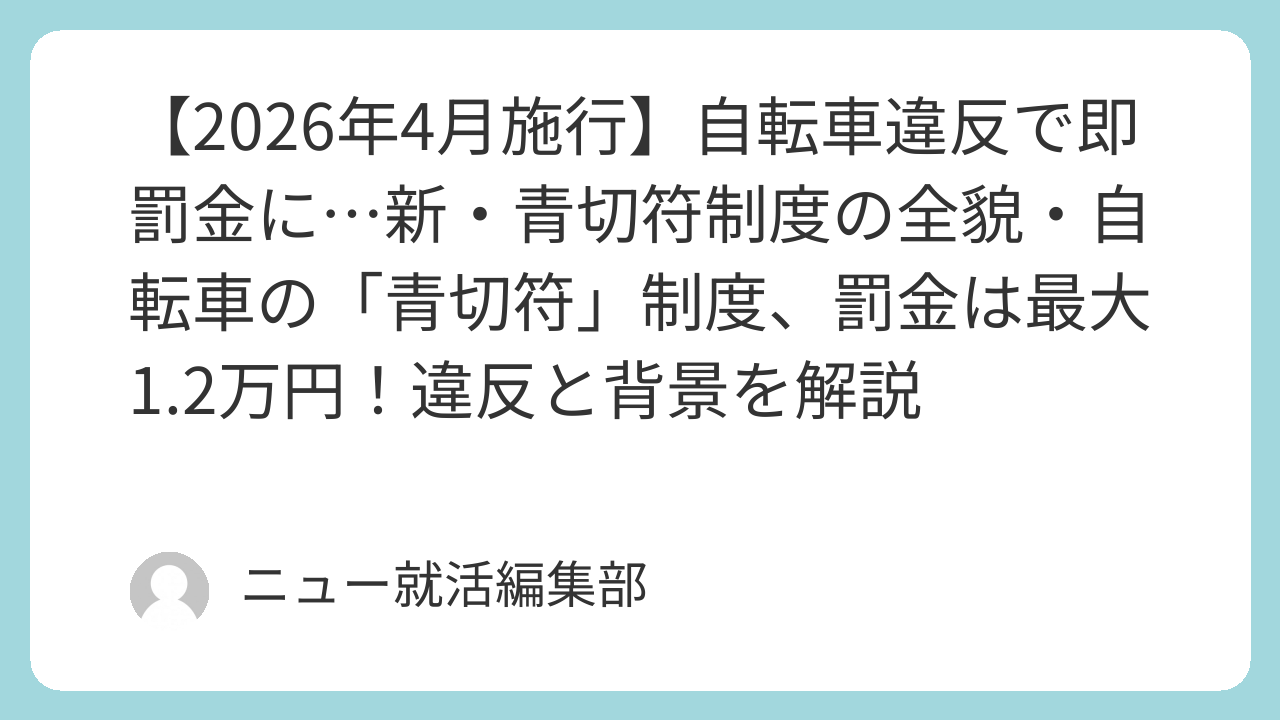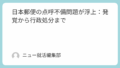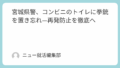青切符制度が自転車にも導入
2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「青切符」による反則金制度が導入されます。青切符とは、交通違反の罰則としてその場で反則金(罰金)を科し、納付すれば刑事罰を免れる制度です。これまで自転車の違反は青切符の対象外で、重大な場合は赤切符(刑事手続き対象の切符)による対応しかありませんでした。改正後は16歳以上の自転車運転者による113種類もの違反行為が青切符の対象になります。ただし、酒酔い運転や妨害運転など重大な違反行為24種類は従来通り赤切符(刑事罰・裁判の対象)となり、検察送りとなります。
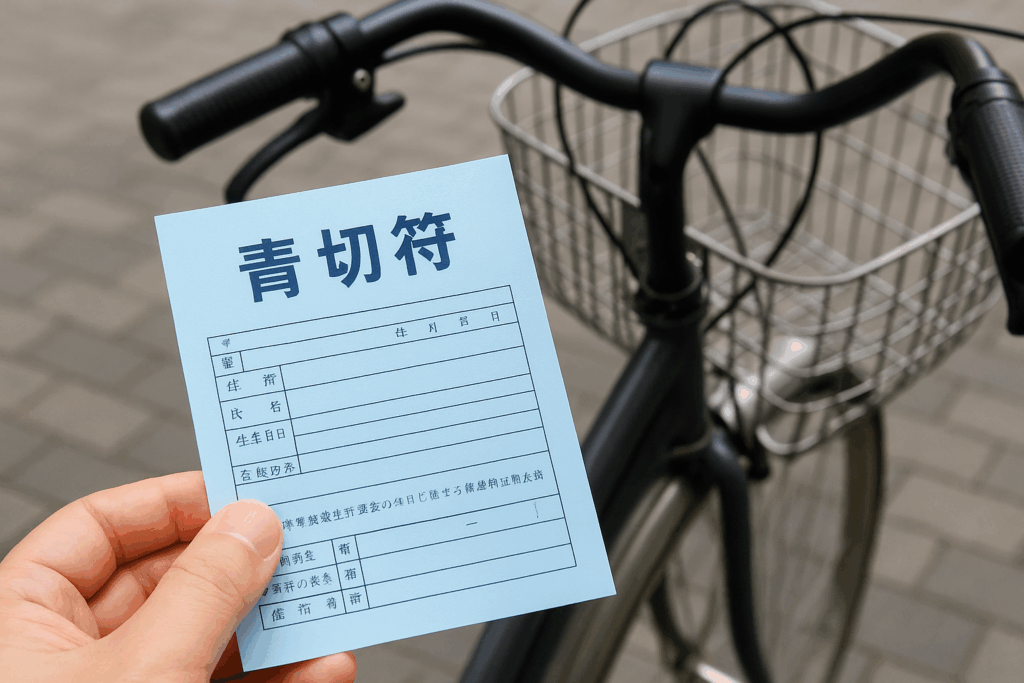
適用される違反と反則金額の例
青切符の対象となる違反には、信号無視や一時停止無視、逆走、スマートフォン使用など多岐にわたります。反則金の額は原付バイクと同程度に設定され、違反内容ごとにおおむね3,000円~12,000円前後です。例えば、ながらスマホ(走行中にスマホを手に持って使用)は12,000円、信号無視は6,000円、右側通行の逆走などの通行区分違反も6,000円、そして自転車の並進走行(横に並んで走る)や二人乗りは3,000円と定められました。これら反則金を違反者が納付すれば刑事罰は科されず済みます。
青切符と赤切符の違いとは?
青切符は比較的軽微な違反に対して交付される反則切符で、違反点数も軽く(※自転車は免許不要ですが、参考として自動車では反則点数6点未満)、反則金を支払えば刑事上の責任は問われません。一方、赤切符は重大な違反時に交付される切符で(自動車では6点以上の違反に相当)、こちらは刑事手続きに移行します。赤切符を切られた違反者は検察による起訴対象となり、裁判で罰金刑や懲役刑が科され、前科(犯罪歴)も残ってしまいます。つまり青切符は行政処分的な罰金で済むのに対し、赤切符は刑事罰の対象になるという大きな違いがあります。今回の改正によって、自転車利用者も今まで以上に交通ルールを厳守することが求められます。
制度導入の背景にあるもの
なぜ今、自転車の青切符制度が導入されるのでしょうか。その背景には自転車利用者の増加と違反・事故の多発があります。近年は通勤通学や移動手段として自転車を利用する人が増え、それに伴い自転車関連の交通違反や事故が社会問題化していました。実際、全体の交通事故件数は減少傾向にある中で自転車が関与する事故の割合は2017年以降増加し高止まりしています。さらに、自転車が当事者となった死亡・重傷事故の約70%で自転車側に何らかの法令違反が認められており、その割合も近年上昇傾向にあります。こうした状況を受け、「悪質な自転車運転者には適切な罰則を科し、再発防止と事故抑止につなげるべきだ」という警察庁の考えのもとで法改正が行われました。以前は軽微な違反でも厳重注意止まりになるケースが多く、取り締まりが追いつかない面がありましたが、反則金制度の導入でその場で迅速に違反切符を切れるようになり、違反抑止効果が高まることが期待されています。
特に危ない「ながらスマホ」運転
数ある違反の中でも、警察が特に危険視しているのが**「ながらスマホ」(スマートフォンを操作しながらの運転)です。近年、自転車事故の中でスマホ使用が関係するケースが急増しており、警察庁の統計によると2023年上半期にはスマホを使用した自転車運転による死亡・重傷事故が計18件(死亡1件・重傷17件)発生し、前年同期の2倍以上に達して過去最悪となりました。また、2017年には女子大学生がスマホ操作しながら自転車を走行して歩行者をはね死亡させる事故も起きており、重過失致死罪で懲役2年(執行猶予4年)の有罪判決が言い渡されています。専門家も「スマホに気を取られた自転車運転手は衝突直前まで歩行者に気づかず、ブレーキをかけないまま衝突することが多い。その結果、歩行者が重傷や死亡に至るリスクが高まる」と指摘しています。こうした重大事故を防ぐため、2024年11月の法改正でながらスマホ運転は正式に禁止行為となり罰則が強化され、冒頭の青切符制度でも反則金12,000円**という重いペナルティが科されることになりました。
おわりに:自転車も「安全運転第一」
自転車は手軽で便利な乗り物ですが、道路交通法の下では自動車と同じ「車両」です。今回導入される青切符制度により、「自転車だから多少の違反は大目に見てもらえる」という時代は終わりつつあります。ルールを守らない悪質な運転には反則金という形で責任が問われるようになります。自転車利用者の方は、改めて交通ルールを再確認し、安全運転を心がけましょう。警察庁も「自転車の利用者はこれまで以上に交通ルールを意識しなければならない」と注意を呼びかけています。歩行者や周囲の車両に思いやりを持ち、事故ゼロを目指して、安全に自転車を楽しみたいものです。